カンボジアは可能性にあふれた国。
トライ&エラーをくり返し、新たな製品を生み出していく。
- 食品事業部
- 冷凍果実
- カンボジア
- 未来への挑戦
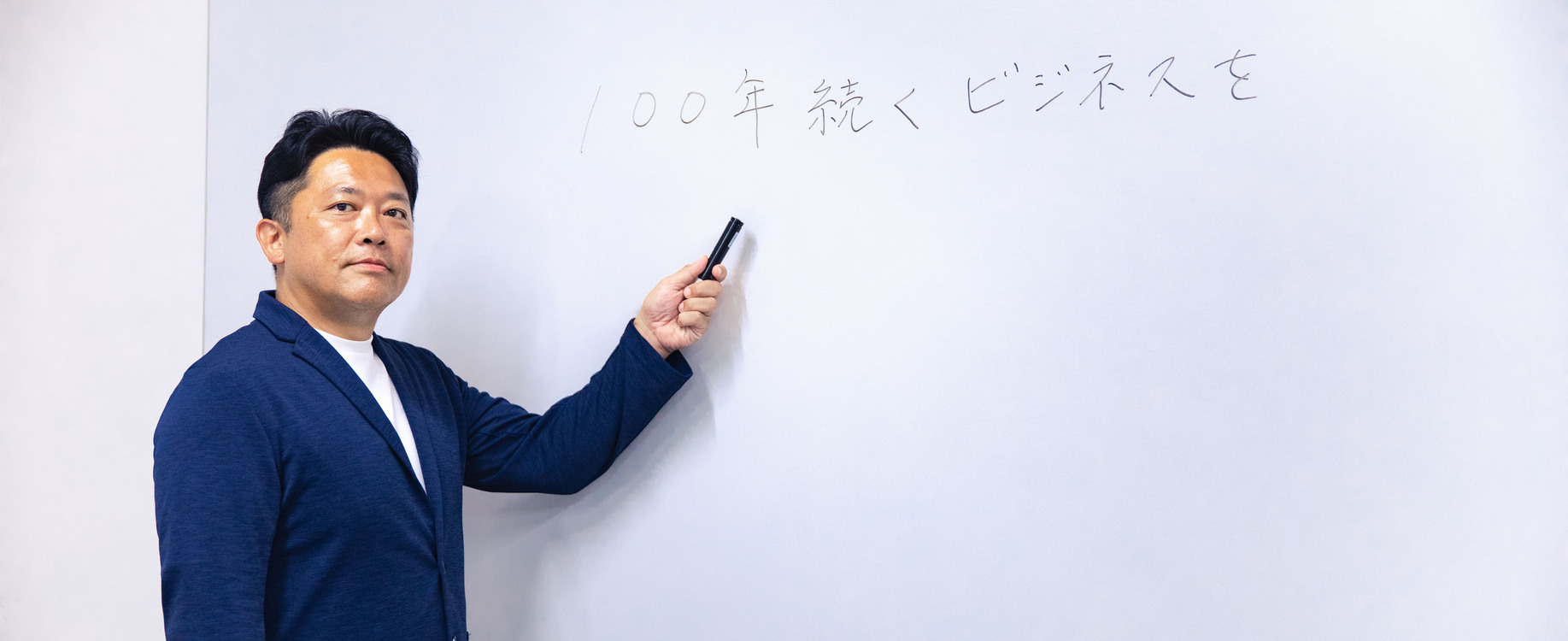
INTRODUCTION
2000年以降、新たな品種である「マハチャノック種」をはじめ、さまざまなマンゴーを日本国内に広めていったヴォークス・トレーディング。
なかでも最近ニーズが高まっているのが、タイの隣国、カンボジア産の「アンコールマンゴー」です。当初は「取引できる品質ではない」と一蹴された品種が、どのように起死回生を図ったのか。プロジェクトを率いた大槻圭さんにお話をうかがいました。
PROFILE
-

食品事業部 事業部長
大槻 圭
1998年にユアサ商事㈱へ入社し、食品本部食品部配属後、生鮮天津甘栗や農水産加工品の開発に携わる。2002年、㈱ヴォークス・トレーディング創業に伴い転籍。その後、タイ産マンゴーをはじめとするTIMFOOD、JAVA AGRITECH製品や冷凍果実・加工食品を担当しつつ、外食ルートの開拓に注力し、ヴォークス・トレーディングの産地開拓と開発力向上に寄与した。2023年、食品事業部の事業部長に就任。
一度は諦めたカンボジアプロジェクト。二度目の挑戦に踏み切ったきっかけは、“地の利”と“TIMFOODの強み”だった

大槻さんは、いつごろからマンゴーという製品に携わっているのですか。
- 大槻
- タイの子会社であるTIMFOODと、インドネシアの子会社であるJAVA AGRITECHの製品担当になった2006年ごろです。タイとハワイの品種を掛け合わせた「マハチャノック種」という新品種の冷凍マンゴーを日本に初めて輸入したのが当社でした。当時はまだ名が知られていない品種でしたが、独特の芳醇な香りと酸味と甘みのバランスに優れた味わいはすぐに市場で高く評価され、大手コンビニエンスストアやフードサービスで使用されるようになりました。
その後、カンボジアでのマンゴー原料調達はどのような経緯で始まったのですか。
- 大槻
- 海外自社工場である TIMFOODは、バンコク市内から北東100㎞程度と、カンボジア国境から比較的近い位置にあります。カンボジアは未知なる土地ではありましたが、内戦から復興を遂げつつあり、経済も成長軌道に入る兆しが見え、私自身、地政学的な魅力を感じていました。そこで2010年ごろから、まずは試験的に短期間で栽培、収穫できるオクラの原料調達を開始。その後はマンゴーの原料調達にも挑戦するつもりでいました。しかし、2年ほど経っても現地の肥培・栽培管理能力が上がらず、効率的な農作物の栽培が難しいということで、カンボジアでのプロジェクト自体が終了してしまいました。
一方、同時期の日本における冷凍マンゴーの需要はますます高まり、日本国内の冷凍マンゴー市場は拡大を続けました。その結果、タイ産マハチャノック種の生産量が需要に追いつかず、市場ではペルー、ベトナム、フィリピン産が台頭する状況となったんです。当社でも冷凍マンゴーの調達ルート拡大を迫られていましたが、我々の矜持として、他社でも取り扱える産地の冷凍マンゴーではなく、誰も取り扱ったことがない産地開発を進めたいと考えていました。そんななか、TIMFOODから「カンボジア産マンゴー原料の調達ができるかもしれない」との一報が入り、すぐに調査を開始しました。カンボジアで日本品質基準のマンゴー原料の調達に成功すれば、当社独自のサプライチェーンを構築することができ、マンゴー事業の拡大と持続的成長も見込めます。そこで、私たちは2015年頃からカンボジア産マンゴーの調達に挑戦し始めました。
最初のプロジェクトが頓挫したあとですが、カンボジアでのマンゴー栽培に勝機はあったのですか?
- 大槻
- その前のオクラ栽培の失敗もありましたので、マンゴーは十分な生産量が見込めるのか、そして我々が要求する品質基準に合致するのか非常に不安でした。前者に関しては、カンボジア産生鮮マンゴーは中国への輸出が増大し、ベトナムにも一定量の原料が流れていることも掴んでいましたので、供給量に問題はないと判断しました。
最大の問題は、後者である品質です。オクラと違い、元々カンボジアではローカル品種のマンゴーが栽培されており、一定の栽培技術はあるだろうと見ていました。品質は非常にバラついていましたが、なかには我々が求める品質の原料も散見され、「やり方次第では形になるのでは」と無理矢理信じ込んでいたのが正直なところです(笑)。
ただし、精神論だけでビジネスは成功しませんので、日本人が駐在し、長年にわたってマンゴーを調達、加工していたTIMFOODの強みを活かせば、必ず高品質の冷凍マンゴーを生産できるはずと考えました。さらに、カンボジアは徐々にインフラが整いつつあり、インターネットの普及により情報入手力が向上、農業技術も発展していたため、カンボジアプロジェクトに再挑戦するタイミングが来たと判断しました。
高品質なマンゴーをつくる。数年間にわたる試行錯誤の結果、カンボジア産マンゴーの市場価値は飛躍的に向上

カンボジアでのマンゴー栽培を再度スタートさせましたが、そのあとの様子はいかがでしたか?
- 大槻
- 正直に言うと、スタートしてからしばらくは品質が全く安定せず、頭を抱える日が続きました(笑)。というのも、原料買付と加工を行うTIMFOODの品質に対する要望を、当初取引していたブローカーに全く理解してもらえなかったんです。溜まる在庫をなんとか捌こうと、私自身も各方面に営業をかけましたが、やっとの思いで成約したユーザーにも品質を酷評される始末。いよいよ終焉を迎えることを覚悟しつつあった時に出会ったのが、TIMFOODの社員に紹介していただいた現パートナーでもあるサプライヤーです。「これが最後ですから」と当時の事業部長(現社長)に頼み込み、規模を縮小した上で生産を進めることで、なんとかカンボジア産原料の冷凍マンゴーを続けることができました。
マンゴーの品質を向上させるためには、どんなところがポイントになるのですか。
- 大槻
- 果実に栄養を行き渡らせるため、意図的に幼い実を間引く「摘果」と、畑の肥料の管理です。元々カンボジアでもローカル品種のマンゴーを生産していましたが、やはり日本で食べられているマンゴーを基準にすると、味わいに大きな差があるんです。それはなぜかと言うと、現地の農家が摘果をきちんと行っていないから。たとえば、10個マンゴーの実がなった場合、通常は半分ほど間引き、残りの実を生育してから収穫します。でも、現地の農家は「10個実がなったなら、10個収穫すればいい」と思っているんです。品質に関しては我々も妥協できない部分ですので、理化学的な検査や、果肉の密度をきちんと調べた上で、基準を下回るものは買付を取り止めるなどしながら、摘果と肥料管理の徹底を求め続けました。その結果、ようやく一定基準の品質を保てるようになり、原料のリジェクト率も少しずつ下がっていきました。
買付後はTIMFOODで原料の冷凍加工を行っていますよね。加工の際のポイントや、他社と比較した際の特徴はありますか?
- 大槻
- TIMFOODでは専用の原料追熟庫を使用し、一つひとつの果実を丁寧にチェックし、熟度を管理しています。その他については企業秘密となっておりますので、ご容赦ください。一つご披露できるとすれば、製造工程で独自の製法を確立していることです。一般的な冷凍マンゴーは解凍するとドリップ(水分)が出るのですが、このTIMFOOD独自の製法で加工した冷凍マンゴーは、解凍しても水分が抜けにくく、生鮮と変わらない濃厚な味わいを楽しむことができます。
マンゴーの「カット&ソース」商品を開発したことも、カンボジア産マンゴーの取扱量増加に寄与していますよね。
- 大槻
- はい。当社のマンゴー製品は「カットマンゴー」として市場でも高い評価をいただいていますが、競合他社の参入による競争が激化しているのも事実です。そのなかで当社が生き残るためには、マンゴーに付加価値をつけた商品の開発が必要です。そこで、2009年ごろに開発した「白桃カット&ソース」をマンゴーでもできないかと思案しましたが、カット&ソース商品を製造には設備投資が必要でした。そのため、例外的に親会社である当社がTIMFOODの設備投資を請け負い、日本人駐在員が必死になって、なんとか「マンゴーカット&ソース」を開発しました。結果的にこの商品は大手外食チェーンで採用され、抜群の広告効果を得ました。
目指すは「100年続くビジネス」。アンコールマンゴー® の商標登録によりブランド化を進める

カンボジア産マンゴーのさらなる拡大のために、取り組んでいることはありますか?
- 大槻
- 「アンコールマンゴー®」の登録商標です。いずれカンボジアや他国製造などの競合品が出てきた場合に備え、違いをはっきりさせるため是が非でも登録したいと思いました。そうすることで、万が一「安かろう悪かろう」のカンボジア産マンゴーが出てきた場合、カンボジアパートナーとTIMFOODでしっかりとした品質のマンゴーを生産すれば、カンボジアマンゴーの価値を守れると考えたんです。
商標登録以降は、展示会にアンコールマンゴー®を持って行くと、“カンボジア産マンゴー≒アンコールマンゴー®”としてより認知してもらえるようになりました。実は登録の過程でもさまざまな苦労があったのですが、みなさんに受け入れられている様子を見ると、結果オーライだと感じます(笑)。また、商標登録や展示会への出展で認知度が上がったことにより、今やアンコールマンゴー®は、ペルー、ベトナム、フィリピン、タイなど各国産のマンゴーと肩を並べられる存在になりました。今後もより多くのお客様に製品を届けることで、アンコールマンゴー®を世界のトップブランドにしたいと考えています。
大槻さんが、現在のアンコールマンゴーに点数をつけるなら何点になるのでしょうか?また、点数を上げていくための、今後の目標や取り組みについてお聞かせください。
- 大槻
- 点数は、現時点で50点くらいではないでしょうか。というのも、私たちのような輸入品を扱う会社は、「原料を生産国内できちんと栽培・加工した上で販売し、結果としてその国の経済に貢献する」ことで、初めてビジネスが成功すると思うんです。今は原料を調達しているだけで、「カンボジアで農作物をつくること」に付加価値をつけられていません。カンボジアの農業×食品加工の発展に寄与するためにも、まずは彼らの財産や価値をいかに高めていけるかが重要だと考えています。また、これを実現するには、「カンボジアとの取引は100年続くのを前提に考える」ことが不可欠です。私もよく「100年続くビジネスを」と社内外で発言していますが、当社と現地のスタッフみんなが力を合わせて、近い将来、マンゴー以外の農産物の栽培・販売へとつなげ、将来的にはカンボジアでの工場建設、生産を実現させたいと思っています。現在もさまざまな取り組みを行っていますので、カンボジア産の製品の動向にみなさんも注目してみてください。
取材日:2025年8月
内容、所属等は取材時のものです


